「ともにネットをなめんなよ」 今年は一度言ってみよう・・
- tomoninet
- 2019年2月13日
- 読了時間: 5分
年末に「こんな夜更けにバナナかよ」をみにいった。原作はともにネットができて間もないころに発刊されている。筋ジストロフィーの鹿野靖明さんの生き様とボランティアとのやり取りを描いたノンフィクションなのだが、「わがまま」ともとれる彼の言動に振り回され、また怒りもおぼえつつ、しかし鹿野の生きざまに惹かれていくボラたち。そして、「迷惑かけなきゃ生きていけないだろ」という鹿野からボラたちは「介助する」「される」という関係を超えた意味合いを探り出していく・・・仕事ではない関係でここまでやれるか、いや仕事じゃないからここまでやれる、仕事の関係の中でもそこはできないのか、ずっと考えてきたことがよぎっていく。
当時、重度の知的障害の人たちの「わがまま」というか「こだわり」の強さに悪戦苦闘しながら、ある線超えると「笑ってしまう」「感心してしまう」ということを体験していた私たちは、この「ある線」は何なのかということを重ねつつ、「こんな夜中に○○かよ」「こんなに毎日○○かよ」とかと半分辛そうに、でも半分嬉しそうに話していたこともあった。
映画が原作をこえることはめったにない。それは自分のイメージで原作を読むのだからこの俳優のイメージじゃないだろうと思うのは当然かもしれない。でもこの映画の鹿野役の大泉洋はなかなかのものだったし、ボラ役で出ている萩原聖人も麻雀だけではないじゃんと思わせるいい味を出していた。
病院を出ようとする鹿野に看護師が無理だ・できるわけがないと止める。高畑充希演ずるボラが「鹿野ボラをなめんなよ」とたんかをきり、地域での暮らしを支えるボラ集めに奔走する。
U・・・m 「ともにネットをなめんなよ」と言える気概を持たねばと思わされた、いい時間だった。
映画つながりで、お勧めのものが2月に劇場公開される。 昨年公開された 「道草」。 監督は宍戸大裕さん。人工呼吸器ユーザーの「風は生きよという」を撮った人だ。 「道草」は重度知的障害者が重度訪問介護の長時間ヘルパーを使いながら一人暮らしをしている様子を紹介している。ヘルパーとのやりとり(せめぎあい)がほほえましい場面だけでなくしんどい場面もまじえ迫ってくる。
新宿ケーズシネマで2月23日(土)から3月8日(金)まで10:20~
前売り券(1300円)ともにネットでもあずかっています。
ご希望の方は声かけてください。
重度知的障害者の暮らしの場(支援)の選択が親元か施設か、そしてグループホームしかないのか、一人暮らしという選択がもっと拡がってもいい。そんなことを私たちに問うてくる映画でもある。ぜひ多くの方にみてほしい。
「介助する」「される」という関係を超えられないのか、仕事の中でもそれはできないのかということを前述したが、このあたりを少し整理してくれた本に出会った。
三井さよ著の「はじめてのケア論」(有斐閣ストゥディア)。いつものようにお風呂に入りながら読むと血圧が上がりそうなくらい、これはどう考えても「はじめての」教科書じゃないと思うが、それはおいといても、私が言葉化できなかったことを表現してくれたところがたくさんあった。
介護・介助や相談・コーディネート、見守りなどの「利用者の日常生活の中に埋め込まれたかかわり」を「ベースの支援」と呼び、その中味を分析していくのだが、とても興味深かった。
ベースの支援の源流は「ともに生きる」運動の中にあったが、現在では仕事として担う人たちも増えてきている。根柢の発想が必ずしも「ともに生きる」でなくとも、見かけ上はそうなっていく面がある。
介護・介助や相談業務を専門職として位置付ける動きがあることも確かである。その背景にはおそらく専門職として位置づけることによって労働条件を整備しようという意図があるのだろう。だが、専門職として位置づけることによって労働条件を整備しようとするのは、いわば希少性によって自らの価値を高めようとするようなものである。なぜそんな回り道をしなくてはならないのだろうか。むしろ単純に、重要で難しい仕事なのだから、それ相応に評価せよと主張すれば良いのではないか。
「失敗」に慣れ、それを前提にマネジメントできるようになるためには、利用者がケア従事者に慣れていなくてはならない。ベースの支援において利用者がケア従事者に慣れているということはすでにケア従事者の能力の一部ですらある。 等など刺激的な視点が示されている。
「『いい加減』の効用」「揺り動かされるのも仕事のうち」などの様々なキーワードをじっくり、ともにネットの支援者とも語ってみたい。
また、「多様性と可変性を担保するために―かたくなさも必要」の項では私も慰められた気もした。
興味ある方は是非読んでみてください。決して「偏っては」いない本ですよ。
1月19日、北多摩北部地域高次脳機能障害者支援ネットワーク協議会主催のシンポジウムに当事者のMさんと一緒に参加してきました。Mさんが事故で高次脳機能障害となり、病院を転々とし、施設入所となり、「こんなうるさいところはいやだ」というMさんの強い思いから地域での自立生活に移行した経過をMさんと一緒に話しました。
日常生活の中で、実はたくさんの「失敗」を繰り返しながらMさんは地域生活を取り戻しているように思います。
故郷のお母さんの顔を時々みにいくことも実現してきましたが、これからは海外旅行にもいきたいそうです。
藤内


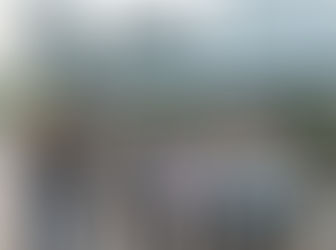



コメント